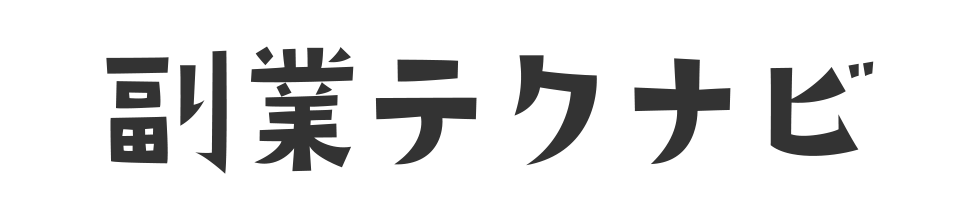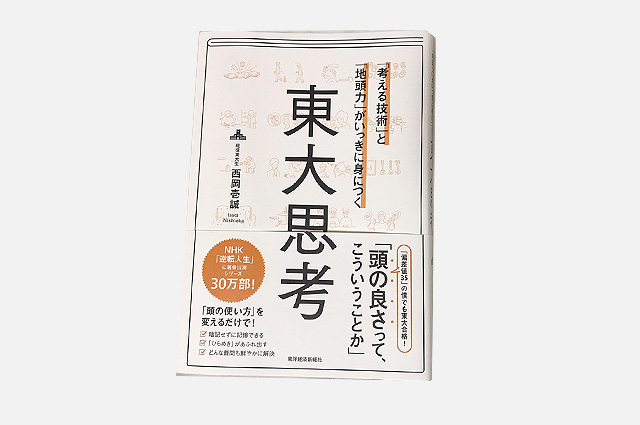本記事では、2020年の夏に初版が発行販売されてからシリーズ30万部を突破した
西岡壱誠(にしおかいっせい)氏の代表本「東大思考」についてざっくり要約をしていきます。
「考える技術」と「地頭力」を身に付ける
あの人は「地頭が良い」といわれる人、あなたの周りにも1人はいますよね?
物事を覚えるのに要領が良かったり、人と違う視点や角度からアイデアや意見を出したり。
これは勉強だけでなく仕事もできるといわれる人たちの特徴であると思います。
それは「もともと才能」がある人。
と思う人もいるかもしれませんが、
著者いわく、これは思考回路の違いだと解説しています。
さらに思考回路を変えて訓練していけば、才能なんて不要とのことです(笑)
「自分には才能がないな」と諦めていた人は、希望が見えてきますよね!
読んでいてなるほど!の連続でした(笑)
しかもあまり関係ないと思う人もいるかもしれませんが
この考え方はウェブデザインやプログラミング、副業の基礎知識やテクニックを磨く際の勉強にも役立ちます。
できれば大学受験の時にこの本に出合っていたかった。。と思うくらい良本です(笑)
購入時は、あとで読もうと思ってましたが一気に読んで大正解でした!
それでは、「東大思考」の本、効率の良い勉強方法や読書法について見ていきましょう。
「東大思考」著者の西岡壱誠氏とは?NHKの「逆転人生」にも出演
その前に少しだけ。
著者はどんな人なのでしょうか。
ざっくり
- 現役東大生である
- 元の偏差値は35
- 社長、顧問を務める
- YouTuber 「スマホ学園」運営
- NHKの「逆転人生」にも出演
こんな方です。なんかすごい人ですよね。
以前に「ビリギャル」と呼ばれ、学年最下位から慶応大学に現役合格した女性の男性版のような方です。
どっちがすごいとかではないですが、ただがむしゃらに勉強をするだけでなく、効率的な方法で成功を収めています。
これは受験を控える大学生だけではなく、社会人にとっても必要なスキル、思考回路なんだなと実感しました。
日常の解像度と5つの思考法
著者は、
あたまのいい人とそうでない人
それは「日常の解像度」に違いがあると解説しています。
解像度といえば画像や写真の鮮明さだったりしますが、
- あたまのいい人:解像度が高い
- そうでない人:解像度が低い
つまり
ポイント
解像度が高いと物事を鮮明に細かく見ることができるけど、
解像度が低い人はピンボケしてはっきりと見る、捉えることができない
と解説してます。
この解像度(思考回路)を高めるには、5つの思考法があります。
それがこちら
- 原因思考
- 上流思考
- 目的思考
- 裏側思考
- 本質思考
それでは、順番にざっくり見ていきましょう。
原因思考
これは「物事には必ず原因がある」という考え方です。
だから常に「なぜ?」と疑問を持ち、原因を探って調べる。
さらに関連付けをして覚えていくということを繰り返していくと膨大な知識量になりかつ記憶を思い出しやすく忘れにくくなります。
例えば、言葉の語源を調べたら派生した言葉や他の意味なども関連付け
1つのことだけではなく複数のことを学んでしまう訳です。
上流思考
これはすべての物事の背景に目を向けようという考えです。
目の前の出来事には前提となることや背景が必ずあります。
これが上流。
そして世の中は下流だらけ。
なので、必ず上流があるので見つける。
この上流がわかると要約もつくる力がつくと解説されています。
目的思考
これは「話がうまい」人は目的がしっかりとしているという考えです。
「何を伝えたいか」が目的。
なのに
多くの人は目的より手段を意識しすぎてふわっとしているとのことです。
営業だったら成果を上げることが目的なのにアポイント(手段)の件数を達成して満足してしまう。
ウェブデザイナーだったら利益を得ることが目的としたら、成果物(手段)を作っただけで満足してしまう。
ように手段をやっているうちに
いつの間にか
手段が目的に変わっている。
ことが多い。
たしかにこういう経験あります(笑)
そして話がうまい人は「説明がうまい」。
コツは2つあって
- 相手の知識に合わせて話す
- たとえ話を使う
ことだそうです。
さらに
相手がわかってくれるだろう
と省略して人へ伝えることはすべきではないと解説しています。
必要な説明を省略したら人へは伝わらないと心得ておく(うーん。これも経験あります。良くないことですよね)
「説明を受けている人を過大評価してはいけない」
裏側思考
これは複数の視点、「一を聞いて十を知る」という考えです。
物事の見る立場や見る方向を変えて物を見るということで、
一から十まで順番に発想が浮かぶ。という意味ではなく、
1つのことに対して10個の見方を持っているということです。
いろんな見方で全体像をつかむ。
頭のいい人は、1つの立場、考え方に縛られずに物事を考える
ことができると解説しています。
それには、
反対意見や否定的なことにも目を向け、違った視点でも物事を見ましょう
ということです。
これはデザインをやっている時のアイデアにも役立つ考えだと強く感じました。
本質思考
これは問題を解決する力のことです。
物事の本質を探る為に、
頭のいい人は
伏線を見つけるのがうまく、
マクロとミクロで物事を考えている。
確かに!
本質がわかっていれば、営業もデザイナーもクライアントやユーザーの問題を提案したり解決することができますよね。
大まかな掴みから具体的なことを掘り下げて本質を見つけ考える。
というスキルは必要だなと感じました。
まとめ
初心者や未経験者であるある
な話で、
営業の仕事だったら
- 話が一方通行でしゃべりまくる
- 自分の考えを曲げない
- 素直になれない
- 相手の意向がわからない
- たとえ話ができない
デザインだったら
- 自画自賛で自分は良いと思う
- 専門用語ばかり使う
- 我流で突き進む
などなど、初めての人が陥りがちなことはたくさんありますが、
この「東大思考」に書かれていることを実践すれば、
ポイント
効率的に知識やスキルを身に付けることにも役立ちますし、コミュニケーション力も向上する
といえます。
結果的に、資格試験の合格だったり営業成績アップ、デザインの採用、副業の質が上がったり良いことばかりかなと感じました。
なので、本当に良い本です。
紹介本
「考える技術」と「地頭力」がいっきに身につく 東大思考
著者:西岡壱誠
発行:東洋経済新報社 2020年08月13日/初版